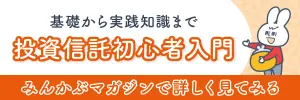100円で資産運用⁉本音の投資信託② 読んでみよう、投資信託のトリセツ(1)

投資信託の目論見書、これを楽しく読んでいます、と言う人はいるだろうか。おそらくほとんどいないだろう。
しかし、これを読んでみることが、資産形成につながる第一歩なのである。少なくとも、私はそう考えている。
そこで、まずは目論見書というトリセツの読み方をお伝えしていくことにする。
そもそもなぜ、投資信託は30年経っても普及しないのか、その理由を考えてみた。
いろいろあると思うが、その一つに目論見書という冊子の存在があるのではないか、そう思うのである。
今では「投資信託説明書」という呼称が使われているが、とにかく、取っ付きづらい。
30年以上業界にいた人間でもそう思うのだから、投資初心者なら尚更だろう。
例えば、投資に全く無関心だった人が、ようやくiDeCoを始めようと思った時にまず面食らうのは、大量に送られてくる資料だそうだ。
中でも商品内容を説明する資料には、もれなくウンザリする、と聞いた。目論見書よりコンパクトにまとめられているはずの資料でさえ、である。
今後も目論見書制度が変わらない以上、まずはこの「投資信託説明書」(目論見書)の読み方、読む際のポイントをお伝えし、少しでも目論見書アレルギーを緩和できれば、と思った次第である。
どんな商品でも、トリセツが読めないと取扱いは難しいものである。
さて、「投資信託説明書」と呼ばれている「目論見書」だが、こう呼ばれるようになったのは2004年のことだ。
そもそも投資信託に目論見書が導入されたのは1998年だが、より使いやすくて分かりやすい目論見書を、ということで、2004年に交付目論見書と請求目論見書に二分割化されることになった。
それに伴って導入された呼称が「投資信託説明書」だった。
1998年以前は、「受益証券説明書」と呼ばれる説明書があり、今のものよりサイズは小さいが、カラーの図や絵・写真などが使われ、もう少し親しみやすいものだった。とはいえ、その頃も投資信託は庶民には近寄りがたい存在だった。
そんな背景ではあるが、投資信託を始めようとする人は、まず「投資信託説明書(交付目論見書)」、つまりトリセツを手元に用意し、これを読み込んで、購入しようとする投資信託について理解することがとても大事なことである。
何だか分からないものを、分からないまま購入してはいけない。
世に「投資信託説明書(目論見書)」の読み方解説はいくつもあるし、長い時間をかけて解説を読んでいては、いつになっても初購入できないじゃないかと思われるかもしれない。
しかし、投資信託は少額で始めることができ、しかも長期積立が似合う商品だ。
だから、安く買って高く売る、という投資のセオリーをそれほど意識する必要はない。焦らなくてもいいのだ。
そういう意味で、ちょっと違うトリセツの解説にお付き合いいただきたい。
次回は、「投資信託説明書(交付目論見書)」の実物を使いながら、具体的な読み方を説明していくこととする。
【関連記事】
配信元:NTTデータ エービック
このコラムの著者

NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
新着記事
最近見た銘柄
投資信託ランキング
2月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト