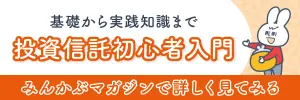投資ブログ紹介!年金繰下げ支給は本当に得?&家族の不幸に備える

今回はにほんブログ村の投資関連ブログランキングの上位ブログの中から、年金の繰り下げ支給は本当に得なのかについて解説している記事と、世帯の資産管理者が急逝してしまうことの問題点と解決案を解説しているブログ記事の2本をご紹介します。
記事タイトル: 年金受給:繰下げ支給は、本当に得をするのか?【年金】
happyoldageさんのブログ
年金受給額を増やすことが可能な繰下げ支給は、本当に得なのかについて解説している記事となります。年金の支給開始期間は原則65歳からになりますが、繰り下げ支給とは年金の受給開始を1年以上遅らせることにより、受給できる年金額を増額できる制度です。
増額する年金額は、繰下げを行った月数×0.7%になり、65歳から70歳まで繰下げ支給を行った場合は0.7%×60ヵ月なので、42%の増額が可能となり、年金受給金額が10万円の場合は、42%の増額になるので、70歳から142,000円の年金を受給することが可能になるとのことです。
デメリットについては、仮に65歳まで働いた場合、繰下げ支給をすると65歳から70歳まで無収入期間となり、この期間の収入をどうすると言うことが問題になります。 また、政府は65歳以上の雇用も可能な制度を検討しているようですが、70歳まで仮に働いた場合、体が持つのかと言う懸念もあります。
厚生労働省が発表している平均寿命、健康寿命によると、男性が日常生活に支障無く健康に生活ができるのは、平均72.14歳となっているそうです。70歳まで働いた場合、生活に支障がない暮らしをできるのは、2.14年となります。女性は、4.79年です。たとえお金がいっぱいあったとしても、体が十分に動かないのでは意味が無いのではとhappyoldageさんは考えています。
ネットニュースなどでFPの方が言うように、年金の増額はたしかに魅力的です。しかし、実際に年金受給を70歳とした場合、65歳から70歳までの無収入期間をどう乗り切るかを考えた場合、パートなどでしのぐと言うこともできるとは思いますが、そこまで働きたいのかと言うと、そうではありません。また、増額された年金をいざ使おうとしても、体が動かず、夫婦で旅行などと言っている場合ではなくなる可能性も高いです。
最後に、繰下げ支給に関しては、65歳の時に申請をしますが、年金受給を開始するときは、自分自身で、請求する必要があるとのことです。70歳になったからと言って、勝手に年金受給が開始されません。その為、年金の貰い忘れの方がいるそうです。税金は、勝手に持っていくのに支給は手続きをしないと貰えないので、気を付けて頂きたいとのことでした。
記事タイトル:家族の不幸に備える 世帯の金融資産管理法
きしやんさんのブログ
先日資産相続やエンディングノートの話をしたので、この記事を作成することにしたそうです。
きしやんさんは、世帯における資産運用とお金の管理は、世帯の中で1番金融リテラシーの番高い人が担当するのが望ましいています。しかし、資産の管理者が急逝しても、残された家族が安心して引き継げるか、について盛り込んでいる世帯はどこまであるでしょうか?と投げかけています。
きしやんさんは家庭の資産運用の基本方針と投資戦略の策定、日々の運用、資産全体の管理を行っています。会社でいうとCIO(最高投資責任者)とCFO(最高財務責任者)を兼務しており、奥様はPCが苦手ということもあり、きしやんさんが急逝すると資産運用保存の観点で非常に脆弱とのことです。
実際きしやんさんが家族を亡くされた際、以下の点に困ったそうです。
①どこの金融機関に
②いくら入ってて
③誰がいくら相続するか
その為、①・②の影響を小さくすることで、相続手続きが終わるまでの私生活への負担を減らすことが可能と考え、以下のような解決案を検討したそうです。
世帯のお金の管理と運用の担当:世帯で金融リテラシーの高い人
世帯資産の保管・運用の口座名義:配偶者
具体的にどのように口座を管理しているかにつきましては、ブログ記事本文に詳細が記載されておりますので、そちらをご参照ください。
【関連記事】
❏投資ブログ紹介!楽天米国レバレッジの長期運用リターン&楽天バランス3姉妹
❏投資ブログ紹介!楽天VTIに関する驚愕の事実!&インデックスファンドは本当に強い?
❏投資ブログ紹介!暴落で分かるファンドの地力&もしも低迷相場が長期化したら
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
このコラムの著者

みんかぶ編集室 (ミンカブヘンシュウシツ)
資産運用のトレンド情報や、初心者が楽しく学べるお金の基本コラムなど、資産形成をするすべての人に向けた記事を提供します。
新着記事
最近見た銘柄
投資信託ランキング
2月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト