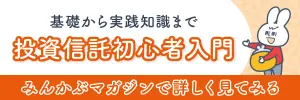シブサワ・レター~こぼれ話~第58回「エジンバラで感じた長期投資の大切さ」

シブサワ・レター ~こぼれ話~
第58回「エジンバラで感じた長期投資の大切さ」
日本資本主義の父 渋沢 栄一 から数えて5代目に当たる渋澤 健が、世界の経済、金融の “今” を独自の目線で解説します。
第58回のテーマは「エジンバラで感じた長期投資の大切さ」です。
謹啓 ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
先月、出張先のロンドンのホテルの部屋で深夜に目が覚めると、つけたままになっていたTV画面に赤い顔をした男性が口を尖らして熱弁を振るっていました。常軌を逸しているなぁと思いながら、再び眠りに落ちました。翌日目覚めた時、あれは時差ボケによる悪夢では無く現実だったんだと、ロンドンの冬空のようにどんよりとした気持ちになりました。
就任したトランプ大統領は即座に米国をパリ協定から脱退させ、米最大手の金融機関や運用会社がネットゼロを目指す国際組織からこぞって抜けるなど、まるでディール・メイクしたような展開に目が点になりました。また就任式でIT長者らの多くが大統領に寄り添っている姿を見ると、これがトランプに票を入れた多くの米国民が望んでいたシーンなのかと首を傾げたくなります。
日本のみならず、世界ではトランプ大統領がこれから何をするかに感心が高いです。ただ、トランプ政権下の米国という現実に対して、むしろ日本の政府・企業は自身の立ち位置や戦略はどうすべきかいうことを、しなやかに実施することの方が重要ではないでしょうか。ピンチには必ずチャンスや新しい展開が訪れるはずです。
翌々日はスイスのダボスで共同議長であるTriple I for Global Healthのサイドイベントを開催しました。途上国に対する米国の開発協力のスタンスが変わることへの懸念は、口に出さなくとも全員の顔に書いてあるようでした。ダボス本会議のムードも絶望的な空気が漂っていたと聞きました。数日後、米国はほとんどの海外協力援助を凍結すると発表しました。
Triple I(https://tripleiforgh.org/)は広島G7サミット首脳会議で承認された日本発のイニシアティブであり、インパクト投資を通じてグローバルヘルス(国際保健)への新たな民間資金の動員を推進しています。トランプの政策転換で米国政府からの資金拠出にブレーキがかかることで、更にグローバルからの関心が寄せられるでしょう。他の国々の政府と民間パートナーたちとのコラボレーションの意識を高めなければなりません。
そして、翌日の早朝にはまた移動して初めてのエジンバラに入りました。イギリスのロンドンから飛行機で1時間ほど北方に移動。天候は変わらず英国の冬空で冷え込んでいましたが、スコットランドの第二の都市に入ると、その街並みに目が奪われます。ロンドンも古い建物が残っていますが、ここでは街全体が数百年も変わっていない。ゆとりある景観に一目で魅了されました。
イギリスからの独自性を表したいという国民の想いが強く、おしゃべりなタクシーの中年運転手によると、特に若手世代が独立志向を支持しているようです。このような何百年も変わらない景観と共に生活を営んでいると、過去の先人から歴史が受け継がれ今の自分が存在しているという意識が高まり、また自分から将来世代へと繋げて行くという感性や責任感が身についているのかもしれないと、帰国後に妻が指摘してくれました。だからかもしれませんが、エジンバラは世界有数の長期投資の運用会社が集まり、世界的な地位を占めています。
このエジンバラの街並みを眺めながら晩年を過ごし、1790年に亡くなったのは市場の「見えざる手」を提唱した経済学者アダムスミスです。市場原理主義の元祖であり、富の不平等の利己的な象徴とされることもありますが、それは「見えざる手」には「道徳感情論」、つまり、同感(sympathy)という社会秩序の土壌があることをしっかりと理解していないからでしょう。渋沢栄一の論語(道徳)と算盤(経済)の合致と通じるものがあります。
スミスのお墓をお参りしながらふと思ったのですが、彼の時代には銀行という存在はありましたが(イングランド銀行の設立は1694年で金を担保に紙幣発行を許された)、近代でいう中央銀行が先進国に設立されたのは1870~1920年頃なので、金融政策によって経済社会の紙幣の量を通じて需給を制御する「手」という概念はなかったのではないでしょうか。
また、財政政策の起源はもっと最近で1930年代の大恐慌です。栄一の時代にも存在していなかった「手」でした。低迷している需要による長期的な失業に政府の財政・金融政策の必要性を説いたジョン・メイナード・ケインズの代表作「雇用・利子および貨幣の一般理論」が出版されたのは1936年です。スミスのように市場自律性を重視し、政府介入を必要としない古典派経済学へのアンチテーゼです。
近代的な金融・財政政策によって需要が生まれ、失業者が減る成果があったことはもちろん否めない現実です。一方、より多くの票を獲得しなければならない民主主義の政治と金融財政政策のカクテルが、現在の経済社会・市場における依存症を生んでいるのではないでしょうか。
政治は取り残された国民を救済するという重要な役割があります。ただ、景気を喚起するという目的で実施された長年の超金融緩和の政策によって、お金の量が過剰に増えると自国通貨の価値が棄損します。そして自国通貨安(インフレ)で最も困るのは保有しているお金が少ない国民層です。お金をたくさん持っていれば、通貨価値が下がっても、生活の支障はありません。
また財政政策という国家介入で新たにカネをばらまくと、まずは貧困層に届くかもしれませんが、彼らの手元には残りません。生活のために使う必要があるからです。そのカネはどこへと流れているのか。もともとお金を持っている層です。
このような目線で金融緩和・財政支出を眺めると、需要喚起策と失業対策という目標の大義の裏に、社会格差拡大という功罪が見えてきます。私は経済学者ではないので、金融緩和と財政支出の政策と格差の因果関係の説明力は乏しいですが、金融・財政政策が誕生してから世界の格差拡大には相関関係があると言い切れます。
米S&P500社の株価指数の時価総額(50兆ドル≒7750兆円)の内、7社だけで30%を示しています。とてつもない富の偏りです。また全く価値をつくっておらず、投機的需給だけで価格が変動するビットコインの時価総額は約300兆円です。アマゾン(上記4位)と肩を並べています。何かがおかしい。これは、明らかです。
長年の政府介入によって、カネの量は世の中の総額で見れば十分に潤沢です。ただ、それが一部に集中していて、全体を浸していない状態が現状ではないでしょうか。その解決策に租税強化を訴える声が少なくありませんが、それにはかなり課題があると思います。なぜなら、世界の超富裕層は租税回避で世界へモビリティがあるからです。結果的に最も税負担がのしかかるのは自国の社会で生活して営んでいる国民階級でありましょう。
経済社会・市場にはカネが有り余っています。足りないのはスミスが250年程昔に示した「同感」(Sympathy)、渋沢栄一が100年ぐらい前に示した「正しい道理」(道徳)ではないでしょうか。ケインズの名言に「長期的には、我々は皆死んでしまう」があります。「我々」は、そのとおりです。ただ、我々の子孫や次世代は長期的には生きて営んでいます。世代格差・倫理を考えると、今のままで良いはずがありません。そんなことをエジンバラの変わらない街並みから感じました。
付録: 「渋沢栄一の『論語と算盤』を今、考える」
(『論語と算盤』経営塾オンラインのご入会をご検討ください。https://bit.ly/3uM0qwl)
「論語と算盤」道徳は進化すべきか
道徳というものまで変化するものであれば、
昔の道徳というものはあまりに尊重すべき価値がなくなるが、
しかし今日理化学がいかに進歩して
物質的の知識も増進して行くにもせよ、
仁義とかいうものは、
ひとり東洋人がさように観念しておるばかりではなく、
西洋でも数千年前からの学者、
もしくは聖賢とも称すべき人々の所論が、
余り変化しておらぬように見える。
時代という次元や東西の壁を乗り越えても、そこには普遍的な想いやあるべき行動は存在するということではないでしょうか。そして、この道徳に大切なカギとは、「自己中」に陥ることなく、公における自分という主体性の表現であると思います。
「渋沢栄一訓言集」道徳と功利
世の富豪が、ただ自家の利益のみを主として、
その事業を経営したならば、それがために
社会のこうむる禍害は、決して少なくない。
アメリカに旅行して見ると、大国だけに
大富豪が極めて多い。もしこれらの大富豪が、
ただ我利主義で社会を跋扈したならば、
一般の国民はいかに困難に陥るであろうか。
商工業は平和の戦争であるから、
その目的は勝つに在るというは、
まったく道徳に背反する行為である。
道徳のかけらも感じられない人物がアメリカの大統領になっている現実では、何が「Great」であるかということを我々自らから考えて実施しなければならない主体性について意識を高めなければならないということでありましょう。そういう意味では、現在の状況は、悪いことではないのかもしれません
謹白
❑❑❑ シブサワ・レターとは ❑❑❑
1998年の日本の金融危機の混乱時にファンドに勤めていた関係で国会議員や官僚の方々にマーケットの声を直接お届けしたいと思い立ち、50通の手紙を送ったことをきっかけとして始まった執筆活動です。
現在は今まで色々な側面で個人的にお知り合いになった方々、1万名以上に月次ペースにご案内しています。
当初の意見書という性格のものから比べると、最近は「エッセイ化」しており、たわいない内容なものですが、私に素晴らしい出会いのきっかけをたくさん作ってくれた活動であり、現在は政界や役所に留まらず、財界、マスメディア、学界等、大勢の方々から暖かいご声援に勇気づけられながら、現在も筆を執っています。
渋澤 健
【著者紹介】
渋澤 健
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役。コモンズ投信株式会社取締役会長。1961年生まれ。69年父の転勤で渡米し、83年テキサス大学化学工学部卒業。財団法人日本国際交流センターを経て、87年UCLA大学MBA経営大学院卒業。JPモルガン、ゴールドマンサックスなど米系投資銀行でマーケット業務に携わり、96年米大手ヘッジファンドに入社、97年から東京駐在員事務所の代表を務める。2001年に独立し、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社を創業。07年コモンズ株式会社を創業(08年コモンズ投信㈱に改名し、会長に就任)。経済同友会幹事、UNDP(国連開発計画)SDGs Impact運営委員会委員、等を務める。著書に『渋沢栄一100の訓言』、『人生100年時代のらくちん投資』、『あらすじ 論語と算盤』他
【関連記事】
□シブサワ・レター~こぼれ話~第57回「"昭和100年” 企業価値の”共創”への期待」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第56回「”行動しないコスト”を意識すべき」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第55回「日本が世界に出遅れている‼デジタル決済」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第54回「新政権に国民を”守る”政策を求める」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第53回「次の政権が落としてはならないバトン ”資産運用立国”」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第52回「株式市場大暴落でワクワクする心得」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第51回「キャッシュレス化が進む中、新紙幣?」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第50回「平和構築のために資本主義を取り戻そう!」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第49回「アブダビで実感した戦略的な投資」
□シブサワ・レター~こぼれ話~第48回「日本銀行の株式ETFは誰のもの?」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第47回「未来フロンティアのアフリカに先行投資する日本企業」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第46回「つみたてNISAは海外でなくても良いんじゃない⁉」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第45回「大変革期の甲辰の主役に期待すべきは企業」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第44回「円安で日本は再び途上国へ⁉」
□シブサワ・レター ~こぼれ話~ 第43回「今回はホンモノか?”貯蓄から投資へ”」
配信元:NTTデータエービック
このコラムの著者
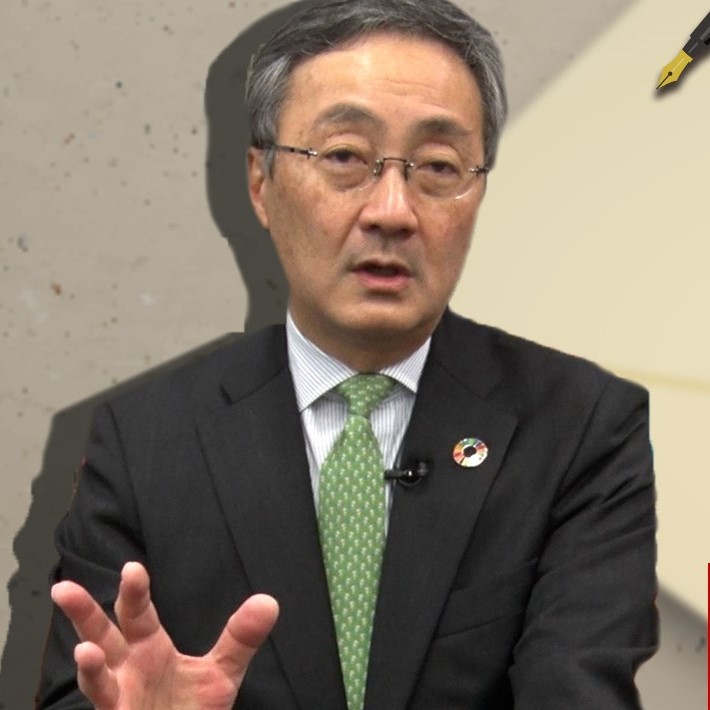
渋澤 健 (シブサワ ケン)
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役。
コモンズ投信株式会社取締役会長。
1961年生まれ。69年父の転勤で渡米し、83年テキサス大学化学工学部卒業。財団法人日本国際交流センターを経て、87年UCLA大学MBA経営大学院卒業。
JPモルガン、ゴールドマンサックスなど米系投資銀行でマーケット業務に携わり、96年米大手ヘッジファンドに入社、97年から東京駐在員事務所の代表を務める。
2001年に独立し、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社を創業。
07年コモンズ株式会社を創業(08年コモンズ投信㈱に改名し、会長に就任)。
経済同友会幹事、UNDP(国連開発計画)SDGs Impact運営委員会委員、等を務める。著書に『渋沢栄一100の訓言』、『人生100年時代のらくちん投資』、『あらすじ 論語と算盤』他。
新着記事
最近見た銘柄
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト